
本番の試験の記述対策として、記述問答集を作ろう!
1.計画の要点、記述が苦手という人は
記述問題、解答用紙を前にすると、何も思いつかない、何を書いていいか分からない。
記述参考文を暗記してみたけど、いざ解答用紙を前にすると、どう書いていいか分からなくて、思考が停止していまう。
その気持ち、よ~く分かります。わたしも、そうでした。「記述、苦手~」って思ってました。
でも、苦手だ~、苦手だ~と嘆いても仕方ありません。合格をもぎ取るためには、記述を克服しないとですね!
記述が苦手と言う方のために、最小限の努力と時間で、記述を克服する方法を紹介します!
まずは、じっくりと「記述とは、何ぞや」を、一緒に考えてみましょう~。

なぜ、苦手なのか?
その理由を考えてみましょう~
皆さんは、自分が、なぜ記述が苦手か、考えてみたことがありますか? 下記は、昨年の課題の記述問題の冒頭部分です。これをもとに、なぜ記述が苦手なのか、一緒に分析してみましょう。
(令和5年度 課題文より)
3.計画の要点等(答案用紙Ⅱに記入)
要求図面では表せない建築物の計画上の要点等について、次の(1)~(7)を具体的に記述又は図示する。
(1) 一般開架スペースについて、次の①、②の観点から配慮したこと
①蔵書数の確保及び書架等のユニバーサルデザイン
②敷地及び周辺条件
(2) 施設の機能構成、配置・動線計画について、次の①、②の観点から配慮したこと
①一般開架スペース、児童開架スペース及び企画展示スペースにおける多世代の交流
②施設の運営管理
「要求図面では表せない建築物の計画上の要点等について、具体的に記述又は図示する」と「配慮したこと」の2つの部分に注目してください。
(※「配慮したこと」という部分は、「考慮したこと」や「工夫したこと」という風に、その年によって若干言い回しが変化していまが、意味合い的には同じことです。)
記述問題の内容は、その年のお題によって変わりますが、下記に示す部分については、毎年同じです。
「図面では表せない、配慮・考慮・工夫したことを、具体的に記述する」
この部分について、一番悩ましいのは、「配慮・考慮・工夫したこと」という、キーワードです。
突然ですが、皆さんは、「配慮・考慮・工夫」していますか?
皆さんはどうか分かりませんが、わたしは、「配慮・考慮・工夫?何それ?」というのが本音で、そんなものをしたことなど一切ありません。
ところが、記述問題は「配慮・考慮・工夫したこと」について問いかけてきます。
「したこと」です。
刑事ドラマじゃないですが、取り調べ室で刑事が「おまえがやったんだろ!」と圧力をかけてきますが、無実の人が「俺は、やってない!」と言うのと似ています。
試験元が刑事とするならば「おまえ、配慮・考慮・工夫したことあるだろ!」と圧力をかけてきますが、あなたは「俺は、やってない!」となる、やってないものは、やってないんです。どう答えろというのでしょうか?
記述が苦手なのは、配慮・考慮・工夫してないのに、それを聞かれるから、答えようがなくて、困惑してまうのが原因です。
「配慮・考慮・工夫」って、しなければならないのでしょうか?
いいえ、しなくても、いいんです。ほんとです。
次は、なぜ、しなくてもいいのか?について、考えてみましょう~。

記述問題、その本質にせまる!?
皆さん!一度、自分が受験者ということを、完全に忘れてください! あなたは、今、採点官です。何十枚もある記述の解答用紙を前に、採点をしようとしている採点官です。 びっしりと書かれた解答もあれば、一言しか書いてない解答もあります。ミミズののたくったような乱字で読めない解答もあります。 それぞれの受験者の「配慮・考慮・工夫したこと」が、解答用紙に書かれています。 どのように採点しますか? 何点を付けますか? 受験者、1人、1人に対して、公平な点数をつけなければ、なりませんよね? あなたの他にも、採点官はいます。各採点官がそれぞれの裁量で点数をつけると、公平性に欠けてきてしまいます。 誰が採点しても同じ点数になるように、何かしらの採点基準が必要です。 何かしらの採点基準があることによって、ようやく、採点官である皆さんは、それを片目に、解答に〇とか×とかの判断を下すことができます。 はい、では、採点官から、受験者に戻ってください。 採点基準、知りたくないですか? 知りたいですよね、それさえ分かれば、それを解答用紙に書くだけで、点数が貰えるんです。 こんな簡単ことはありません。 皆さんは、採点基準、どんなことが書かれていると思いますか? もしもですよ? 下のAとBの採点基準があるとします。より、公平な採点ができる採点基準として、最適なのはどちらだと思いますか? A:解答文が、その人の思想を反映した内容になっていて、配慮・考慮・工夫した内容が素晴らしい。 B:解答文が、大学に求められるニーズにおいて、配慮・考慮・工夫すべき項目が解答されているかどうか。 わたしは、Bだと思います。「公平な採点ができる採点基準」、絶対Bですよね。 だけど、解答用紙の前にしたあなたは、Aを一生懸命に解答しようとしていませんか? その努力、残念ながら、意味がありません。同じ努力をするなら、Bの採点基準に合わせた解答をしましょう。 Bの採点基準は「大学に求められるニーズにおいて、配慮・考慮・工夫すべき項目」です。 Bの採点基準には、これこれ、こういう項目が解答文に含まれているか?などをチェックするような、明確な設定がされているだろうと、わたしは思います。 「大学に求められるニーズ」をチェックする採点基準、、、。 「大学に求められるニーズ」って何でしょうね? それについは、過去ブログで紹介した「設計方針」を参照してみてくださいね。
さて、今、考えてきた内容を踏まえて、もう一度、計画の要点の課題文を、読んでみてください。
図面では表せない、配慮・考慮・工夫したことを、具体的に記述せよ。
この課題文で、試験元は、本当は、こう、聞きたいんです。
図面では表せない、大学に求められるニーズにおいて、配慮・考慮・工夫すべきことを、具体的に記述せよ。
「したこと」と「すべきこと」では、全然、意味が違ってきますよね!!
「配慮・考慮・工夫したことについて記述せよ」には解答できなくても、「配慮・考慮・工夫すべきことについて記述せよ」には解答できそうな気がしませんか?
自分が「してない」ことは答えようがありませんが、「すべきこと」なら答えることができますよね!
やってなことも、でっち上げてもいいってことですもの!!
しかも、都合のいいことに「図面では表せない」とわざわざ言ってくれています。
図面と関係ないところだったら、何を書いてもいいよ~と言ってくれているようなものです!!
それなら、図面と関係ないところで、ほんとはやってないけど、「大学に求められるニーズ」から考えるなら、本来、やっておくべきなんだろうな~ってことを、解答すれば良さそうじゃないですか?

えっ、
大学に求められるニーズが、わからない?
大丈夫です、とっても良い資料がありますよ!
じゃ、その「大学に求められるニーズ」とやらは、何なのか?どうやって調べたらいいのか? 今年の受験者は、ラッキーです。 あれこれ調べる苦労をしなくても大丈夫です。 文部科学省が、大学に必要な「ニーズ」の資料を出してくれています。ぜひ、活用してください! その資料とは、文部科学省のサイトにある【国立大学等施設設計指針】と【国立大学等施設の設計に関する検討会報告書】になります。 資料の名称が長いので、これから以降は、下のように表記しますね。 国立大学等施設設計指針 → 指針 国立大学等施設の設計に関する検討会報告書 → 報告書
2.記述問答集を作ろう
さて、前置きが長くなってしまいましたが、皆さんに提案があります。
「記述問答集」を作ってみませんか?
記述の参考例文を一生懸命に暗記したのに、いざ解答用紙を前にすると、フレーズは思い浮かぶけど、そのフレーズをどう組み立てて、文章にしていいのか、いつも悩んでしまって上手くいかない。と言う人は少なくないと思います。
かく言うわたしも、そんなタイプです。
不合格だった年の製図試験でも、悩みに悩んで試行錯誤した結果、書けたのが一行程度、解答用紙はスカスカです。
合格した年の製図試験は、どうだったか? 解答用紙にびっしりとはいきませんが、それなりのボリュームは書くことができました。
しかも、割と悩むことなくスムーズに書くことができました!
不合格だった年と、合格した年の違いは、なんだったのか?
実は、合格した年は、暗記はほとんどしていません。高齢者介護施設(わたしが受けた年の課題です)と言う建物は、どうあるべきなのか?ということについて、ひたすら調べたり、自問自答を繰り返していました。
その時には、記述対策になるとは思っていませんでしたが、結果的には、記述対策になっていたんだなぁ。と、今、振り返ってみると、そう思います。
人というのは、不思議なもので、いくらもっともらしい説明文を暗記しても、それを、いざ誰かに説明しようとすると、なかなかうまく説明ができないものです。
なぜなのかは、分かりません。暗記した説明文を、ただ、相手に伝えるだけなのにです。不思議ですよね。
結局は、自分自身で深く考えて、自分が納得できるところまで理解する。それで、やっと、他人に説明できるようになる。こういう、よくは分からないんだけれども、どうしようもない事象には従うしかありません。
さて、学科では繰り返しの暗記、作図では時間短縮のためにひたすらトレース、それに加えて、記述では「理解」する、あの手・この手、いろんな手段を使わなくちゃいけないなんて、大変ですよね。
ですが、記述は、学科や作図と違って、繰り返しの鍛錬のための時間を費やす必要がないのがメリットですよ。
記述は、「理解の習熟」を目指せばいいのですから、鍛錬系じゃありません、頭脳戦です。
「理解の習熟」に必要なのは、思考力だけです。いかに深く考えて、自分の血肉にするかだけです。
その「理解の習熟」の一つとして、わたしから提案があります。
「記述問答集」を作ってみてください!
「記述問答集」自体には、意味がありません。
作る過程に、とても意味があります。
作ってみれば、自ずと気づくと思いますが、「理解」しないと、「記述問答集」を作ることができないんですよ!
自身で、実際にやってみれば、分かりますよ~。ぜひ、チャレンジしてみてください。
「記述問答集」作成の手順を説明しますね。
1. 指針と報告書をダウンロードします。
2.下図のように、指針及び報告書の中から、本番の試験と同じような文章になるように質問文をつくります。
本番試験と同じ文章になるようにするコツは、
「〇〇について、〇〇の観点から、配慮したことを記述または図示せよ」の定形文に、
フレーズを入れるとうまくいきます。

👇
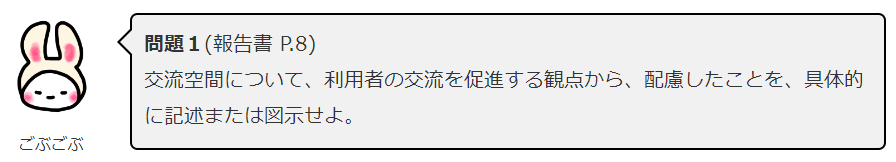
3. 下図のように、今度は自分で考えた質問文に対して、指針及び報告書の中から、解答をみつけて解答文をつく ります。
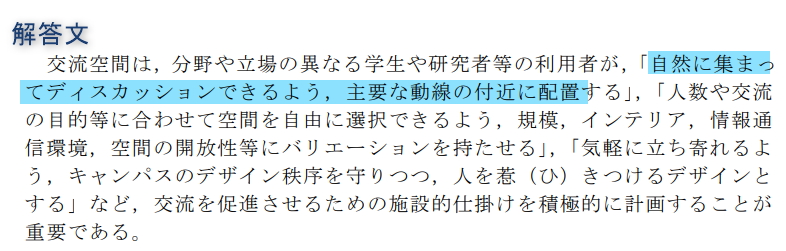
👇
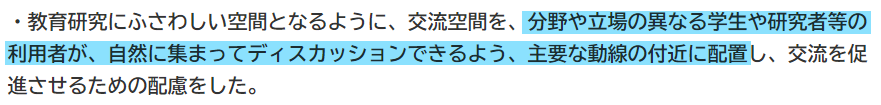
指針と報告書から、できるだけたくさんの問答を作ってくださいね。それが、あなたオリジナルの「記述問答集」になります。いえ、「自問自答集」になります。
下の方に参考の問答集を載せています。自分で作っている暇がないという方は、良かったら、利用されてください。
利用される際は、問題文に指針と報告書のページが書いてありますので、該当箇所を参考に、解答文を実際に作ってみることをお勧めします。
暗記よりも、理解することの方が、とても大切ですよ~。
3.参考:記述問答集 37問
交流空間とは、「大学設置基準」で言うところの「空地」のことです。まだ「大学設置基準」をチェックしていない方は、こちらのブログ記事を参照してくださいね。
本試験では、交流空間ではなく、「コミュニケーションスペース」、「交流スペース」、「交流ラウンジ」、「学生ラウンジ」、「リフレッシュスペース」とかのいろんな呼び方で主題してくるかもしれませんが、全て同じ意味です。

問題1(報告書 P.8) (指針 P.3)
交流空間について、利用者の交流を促進する観点から、配慮したことを、具体的に記述または図示せよ。
・教育研究にふさわしい空間となるように、交流空間を、分野や立場の異なる学生や研究者等の利用者が、自然に集まってディスカッションできるよう、主要な動線の付近に配置し、交流を促進させるための配慮をした。
(図示:「交流空間」とその周りの「要求室」と「廊下」の簡単な配置図に、交流空間に自然に集まってくるような「動線」の矢印を加えた説明図をつける。)
・教育研究にふさわしい空間となるように、交流空間を、分野や立場の異なる学生や研究者等の利用者が、人数や交流の目的等に合わせて空間を自由に選択できるよう、規模、インテリア、情報通信環境、空間の開放性等にバリエーションを持たせ、交流を促進させるための配慮をした。
(図示:「交流空間」内を、ただテーブルや椅子だけの什器を置くのではなく、例えば自習が行えるPCスペース、ディスカッションをするのに適した空間ととするためにホワイトボードや黒板などを設置できる壁の周りに椅子を配置したスペース、休憩できるリラックスした雰囲気のための吹き抜け空間、等々のバリエーションの説明図をつける)
・教育研究にふさわしい空間となるように、交流空間を、分野や立場の異なる学生や研究者等の利用者が、気軽に立ち寄れるよう、キャンパスのデザイン秩序を守りつつ、人を惹きつけるデザインとすることで、交流を促進させるための配慮をした。

問題2(報告書 P.8)(指針 P.3)
各要求室について、ユニバーサルデザインの観点から、配慮したことを記述せよ
ユニバーサルデザインの観点から、多様な人々が円滑に利用できるよう、部屋等を分かりやすく配置するとともに、案内・誘導するためのサインの視認性・可読性を高めるなど、利用者の快適性・利便性への配慮をした。

問題3(報告書 P.8)(指針 P.3)
講義室・実験室・研究室について、快適性の観点から、配慮したことを記述せよ。
講義室・実験・研究室等の教育研究の中核となる空間については、利用者がストレスなく学修等に集中できるよう、その活動に応じた、熱、空気、光・色彩、音・振動の室内環境を整えるとともに、窓からは緑豊かな美しい景観が見えるなどの快適性に配慮した。

問題4(報告書 P.8)(指針 P.4)
通路・階段・エレベーター・トイレ・リフレッシュスペースについて、利便性の観点から、配慮したことを記述せよ。
学修の合間等に利用する通路・階段・エレベーター・トイレ・リフレッシュスペースについては、利用人数、利用時間、利用の集中等を考慮した規模とし、常に清潔な空間となるよう、施設管理者と連携がしやすい清掃等の運用に考慮した平面計画や設備計画とし、利便性への配慮をした。

問題5(報告書 P.9)(指針 P.4)
エントランスホールについて、多様な教育研究活動の観点から、配慮したことを記述せよ。
エントランスホールについては、多様な教育研究活動に合わせて活用できるよう、学生が自由にプレゼンテーションや行えるなどの可変性を有した空間となるよう配慮した。

問題6(報告書 P.9)(指針 P.8)
施設の地震対策について、構造体の耐震性能以外で防災機能強化の観点から、配慮したことを記述せよ。
施設の地震対策については、構造体の耐震性能の確保はもとより、外装材、天井、照明器具等の落下防止や実験装置等の転倒防止等の対策に配慮した。

問題7(報告書 P.10)(指針 P.8)
施設の地震対策について、構造体の耐震性能以外で利用者の避難の観点から、配慮したことを記述せよ。
施設の地震対策については、構造体の耐震性能の確保はもとより、発災時に学生や教職員等の利用者が円滑に避難できるよう、計画段階から、わかりやすい動線やサイン等に配慮した。

問題8(報告書 P.10)(指針 P.9)
実験室について、利用者の安全性の観点から、配慮したことを記述せよ。
実験室については、薬品等の使用時に発生する可能性がある有害ガス等のばく露を防ぐため、室内の空気の流れを考慮し、実践機器や局所排気等の設備等を適切に配置するなどして、利用者の安全性に配慮した。

問題9(報告書 P.11)(指針 P.9)
施設について、セキュリティーの観点から、配慮したことを記述せよ。
施設について、盗難や傷害等の犯罪を未然に防止するためには、監視によるけん制がある程度有効であることから、必要に応じて監視カメラ等の設置などを検討し、施設の各部に死角を生じないよう視認性を高めることに配慮した。

問題10(報告書 P.11)(指針 P.10)
施設の長寿命化について、配慮したことを記述せよ。
施設を長期間使用していくために、適切なメンテナンスが行えるよう、設備の更新・増設のためのスペースの確保や更新、メンテナンスのしやすさに配慮した。

問題11(報告書 P.11)(指針 P.10)
施設について、省エネルギーの観点から、配慮したことを記述せよ。
・施設の省エネルギーについては、外壁や窓等の高断熱化、庇や樹木等を活用し、屋外環境をコントロールすることによる熱負荷の低減、照明・空調設備の高効率化等、また太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの利用よる創エネルギー良好な室内環境とエネルギー使用の合理化を両立させることに配慮した。

問題12(報告書 P.12)(指針 P.11)
施設について、二酸化炭素排出量削減の観点から、配慮したことを記述せよ。
・施設の二酸化炭素排出量削減については、使用材料の設定にあたって、コストに配慮しつつ、環境負荷の少ない木材等の自然材料や再生材料の使用を検討することに配慮した。

問題13(報告書 P.12)(指針 P.11)
施設について、地域環境の観点から、配慮したことを記述せよ。
・施設の外観デザインについては、歴史と伝統の継承等を踏まえ、キャンパス内外の景観、施設群としての調和に配慮し、良好な地域環境を形成することに配慮した。
コミュニケーションスペースとは、「大学設置基準」で言うところの「空地」のことです。まだ「大学設置基準」をチェックしていない方は、こちらのブログ記事を参照してくださいね。
本試験では、コミュニケーションスペースではなく、「交流空間」、「交流スペース」、「交流ラウンジ」、「学生ラウンジ」、「リフレッシュスペース」とかのいろんな呼び方で主題してくるかもしれませんが、全て同じ意味です。

問題14(報告書 P.21)(指針 P.5)
コミュニケーションスペースについて、大学機能の活性化の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・コミュニケーションスペースについては、オープンな雰囲気の醸成、各分野間のコミュニケーションの機会を生み出し、情報の発信拠点として、情報の共有化や効率的な情報収集を促進等による大学機能の活性化に配慮した。

問題15(報告書 P.21)(指針 P.5)
コミュニケーションスペースについて、空間構成の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・コミュニケーションスペースについては、様々な交流に対応できる空間規模と可変性、出会いと会話を促す空間構成と什器等の配置、カフェ等のサービス機能と緑化等のリフレッシュ機能の組み合わせ等の空間構成に配慮した。

問題16(報告書 P.21)(指針 P.5)
コミュニケーションスペースについて、環境・設備性能の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・コミュニケーションスペースについては、各種展示やミーティングに対応したICT環境、利用目的に応じて設定が可能な照明設備、他の部屋への音の影響に配慮した音響計画等の環境と設備性能に配慮した。

問題17(報告書 P.21)(指針 P.5)
コミュニケーションスペースについて、運用面の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・コミュニケーションスペースについては、全学的な利用や学外の利用も踏まえた共用施設としての利用、機能・デザイン・レイアウトに配慮した什器、清掃等のサービス体制等など運用面に配慮した。

問題18(報告書 P.22)(指針 P.5)
学修スペースについて、大学機能の活性化の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・学習スペースについては、電子情報や印刷資料を含む情報資源を用いて学生の主体的な学びや活発なディスカッションを支援するための設備や什器等を配置できるよう大学機能の活性化に配慮した。

問題19(報告書 P.22)(指針 P.5)
学修スペースについて、空間構成の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・学修スペースについては、様々な利用形態に対応できる空間規模と可変性、利用状況が把握しやすい視認性の確保と適度なプライバシーを保つ距離の設定等の空間構成に配慮した。

問題20(報告書 P.22)(指針 P.5)
学修スペースについて、環境・設備性能の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・学修スペースについては、プレゼンテーションやグループディスカッション等に対応したICT環境、利用目的に応じて設定が可能な照明設備、自習やディスカッション等に配慮した遮音性等を考慮した環境・設備性能に配慮した。

問題21(報告書 P.22)(指針 P.5)
学修スペースについて、運用面の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・学修スペースについては、様々な空間と活動が混在することを踏まえた利用形態、什器等を収納するスペースの確保、機能・デザイン・レイアウトに配慮した什器等、清掃等のサービス等の運用面に配慮した。

問題22(報告書 P.23)(指針 P.6)
講義スペースについて、大学機能の活性化の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・講義スペースについては、教員の様々な講義形態に対応できる空間規模と可変性等に考慮し大学機能の活性化に配慮した。

問題23(報告書 P.23)(指針 P.6)
講義スペースについて、空間構成の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・講義スペースについては、様々な利用形態に対応できる空間規模と可変性、講義内容が聞き取りやすい吸音(防音)仕様と他の部屋に配慮した遮音性能等の空間構成に配慮した。

問題24(報告書 P.23)(指針 P.6)
講義スペースについて、環境・設備性能の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・講義スペースについては、ICT環境やAV設備、多人数の利用に対応できる環境制御(空調設備、換気設備、照明設備)などの環境・設備性能に配慮した。

問題25(報告書 P.23)(指針 P.6)
講義スペースについて、運用面の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・講義スペースについては、講義の内容に合わせ操作がしやすいICTツールの導入、全学的な利用や学外の利用も踏まえた利用形態、稼働率を高める仕組みと工夫、機能・デザイン・レイアウトに配慮した什器等による運用面に配慮した。

問題26(報告書 P.24)(指針 P.6)
実験・研究スペースについて、大学機能の活性化の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・実験・研究スペースについては、研究者間の情報共有と活発なディスカッションを通じ、自由な交流や共同研究を推進すること、実験研究への集中と気分転換(休憩)の両立等に考慮し大学機能の活性化に配慮した。

問題27(報告書 P.24)(指針 P.6)
実験・研究スペースについて、空間構成の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・実験・研究スペースについては、実験や研究内容の変化等に対応できる空間規模と可変性、機能的な内装使用等等の空間構成に配慮した。
・実験・研究スペースについては、実験・研究活動に対応する作業エリアと通路の確保、避難上の安全性の確保、作業状況等が確認できる視認性の確保等の空間構成に配慮した。

問題28(報告書 P.24)(指針 P.6)
実験・研究スペースについて、環境・設備性能の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・実験・研究スペースについては、設備等のメンテナンスのしやすさ、実験・研究に対応した良好な室内環境を維持できる空調設備や換気設備等に関する環境・設備性能に配慮した。

問題29(報告書 P.24)(指針 P.6)
実験・研究スペースについて、運用面の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・実験・研究スペースについては、設備等の適時適切な維持管理、安全衛生管理対策を踏まえた全学的な利用形態等に関しての運用面に配慮した。
・実験・研究スペースについては、機能・デザイン・レイアウトに配慮した什器等、共有スペースを設けて機器等の共同利用を図ることで交流を促すような工夫の運用面に配慮した。

問題30(報告書 P.25)(指針 P.7)
教員スペースについて、大学機能の活性化の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・教員スペースについては、各教員の能力向上と教員間の連携を促進すること、研究者間の情報共有と活発なディスカッションを通じ、自由な交流や共同研究を促進すること等の大学機能の活性化に配慮した。

問題31(報告書 P.25)(指針 P.7)
教員スペースについて、空間構成の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・教員スペースについては、研究内容や組織の変化に対応する可変性、集中を阻害しない工夫と視認性の確保とのバランス、教員間の交流を促す工夫と気密性を保つ空間とのバランス等の空間構成に配慮した。

問題32(報告書 P.25)(指針 P.7)
教員スペースについて、環境・設備性能の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・教員スペースについては、ICT環境、多人数の利用に対応できる環境制御(空調設備、換気設備、照明設備)等に関する環境・設備性能に配慮した。

問題33(報告書 P.25)(指針 P.7)
教員スペースについて、運用面の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・教員スペースについては、誰もが快適に共有して利用できる利用形態、機能・デザイン・レイアウトに配慮した什器等の運用面に配慮した。
・教員スペースについては、共有スペースを設けて機器等の共同利用を図り、交流を促す工夫に関しての運用面に配慮した。

問題34(報告書 P.26)(指針 P.7)
災害対応について、大学機能の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・災害対応については、発災時の学生・教職員等の安全性の確保すること、地域の防災拠点として緊急避難場等を設備することに配慮した。

問題35(報告書 P.26)(指針 P.7)
災害対応について、配慮したことを、記述せよ。
・災害対応については、構造体の耐震性の確報、非構造部材等の落下・転落防止、建物接合部の補強・落下防止等にに配慮した。

問題36(報告書 P.26)(指針 P.7)
災害対応について、環境・設備性能の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・災害対応については、緊急時にも対応できる放送設備・通信設備・照明設備等に関しての設備性能に配慮した。
・災害対応については、太陽光発電設備や風力発電設備等による独立した電源システム等の設備性能に配慮した。
・災害対応については、冬期の被災を想定した暖房設備、マンホールトイレや仮設トイレ等の環境に配慮した。

問題37(報告書 P.26)(指針 P.7)
災害対応について、運用面の観点から、配慮したことを、記述せよ。
・災害対応については、防災備蓄の確保のための防災備蓄スペース等に配慮した。
4.参考:記述問答集 +2問
以下の2問は、指針・報告書には記載されていませんが、ついでに付けておきます。
この2問についての詳細は、また次回のブログでご紹介したいと思います。

問題38
大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画について、考慮したことを記述せよ。
・構造計画については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画規準」に基づき、構造体はⅡ類(重要度係数を1.25倍)、建築非構造部材はA類、建築設備は乙類と設定し、建築物の機能が維持できるように考慮した。

問題39
段床形式の講義室(200席)について、バリアフリーの観点から、配慮したことを、記述せよ。
・段床形式の講義室については、車椅子の席は幅90㎝x奥行135㎝以上で区画された平らな床とし、サイトラインの確保に配慮した。
5.まとめ
記述が苦手な人のための克服方法を、ご紹介しました。
わたし自身が、記述が苦手だったので、記述が書けないという人の気持ちが、よく分かります。
ご紹介した克服方法は、そんな、わたしの経験がもとになっています。
全ての人に、有効かと言われると、たぶん、違うと思います。
でも、何かしらのヒントになって、記述の苦手意識を克服して、合格を掴み取る手助けになったら、幸いかな~なんて思います。
記述の克服に「努力」は不要です!
必要なのは「気づき」と「ニーズの理解」です!
一級建築士の製図試験を、「自分」を捨て「建築士という仕事人」の立場で、眺めてください。
普段、お仕事で頑張っている皆さんにとって、記述は「大したことない」ものに、きっと変わると思います。
それでは、また。




